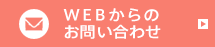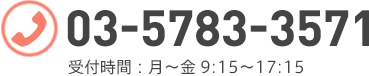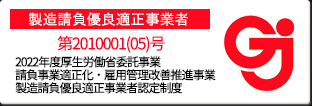お知らせ
2017/12/12
忘年会シーズン気をつけましょう「お酒が招く精神不調」
企業の職場では、年末になるとほぼ例外なく忘年会が開かれます。職場の皆さん方の懇親を図るために有意義ですが、「お酒が招く精神不調」にも気をつけてください。新年会も同様です。職場でのメンタルヘルス対策の立案・実施にあたっては、平山のEAPコンサルタントのアドバイスがお役に立つと思います。ぜひお声をおかけください。
パニック症の患者さんに一年のうち何月が最も具合が悪いかをアンケートしたことがある。案の定6~8月は悪く、秋冬は快調との答えが多かった。ただし、冬のうち12月だけは例外だった。理由は単純、忘年会だ。年末の忙しさに忘年会の飲酒が輪をかけて症状を悪化させる。
飲酒と不調の関係はパニック症に限らない。うつ病など他の病気の人はもちろん、精神不調とは無関係と思いこんでいる人にも当てはまる。飲酒をやめたり減らしたりするだけで、不安発作が減り、落ち込みやイライラが軽くなる例は珍しくない。
~なぜ楽しい飲酒が精神不調につながるのか~
なぜ楽しい飲酒が精神不調につながるのか。納得のいかない人もいると思うので、少し説明しよう
お酒の中身は神経に働く「エチルアルコール」だ。神経に働くあらゆる化学物質には「作用」と、それが切れた時の「反動」がある。お酒で気分が高揚し、不安や緊張が和らぐのは、実際に飲んでいる間だけ。飲み終わって作用がピークを過ぎると、すぐ反動が表れ、作用と正反対のことがおきる。アルコールの場合、気分の落ち込み、不安や悲しみの増大などで、不安発作も誘発される。
~より大きな問題は「自殺」への影響~
より大きな問題は「自殺」への影響だ。これは「反動」で絶望感が生ずるだけではない。「死にたい気持ち」を毎日何とか我慢してきた人を自殺へと後押ししてしまう。
実際、アルコール消費の多い地域は自殺率が高く、旧ソ連ではアルコール製造を制限した1980年代、一時的に自殺数が激減した。
~やはり飲酒はほどほどにすべし~
約100年前に米国でできた禁酒法が密造酒とギャングの暗躍などで撤廃されたように、今の日本社会で酒をなくすのは非現実的だが、やはり飲酒はほどほどにすべきだろう。特に何らかの精神的困難を抱えている人には節酒、できれば禁酒を勧めたい。また、忘年会続きは睡眠不足も招くので、皆さん体調を十分に考えて。新年会も同様だ。
(東京大、精神科医 佐々木司教授、2016年12月4日毎日新聞より抜粋)

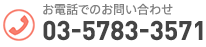
![[受付時間]月~金9:15~17:15](/images/common/header_time.png)